- 開催期間
- 2025年12月12日(金)~12月24日(水)
*館内工事・展示替えのため、12月25日(木)・26日(金)は休館いたします。 - 開館時間
- 10:00~19:00
*12月24日(水)は19:00まで
(入館は終了10分前) - 会場
- 富士フイルムフォトサロン 大阪 スペース1・スペース2・ホワイエ
- 入場料
- 無料
年度別リスト
全世界から選ばれたクリエイター15名の作品がついに完成!
富士フイルム 企画写真展
GFX Challenge Grant Program 2024
~Make Your Next Great Image~
富士フイルムが主催する「GFX Challenge Grant Program 2024」は、世界各国・地域で活躍するクリエイターの創作活動サポートを目的とした助成金プログラムです。
2024年7月から9月にかけて、全世界を3つの地域に分け各地域の写真家から、助成金を活用し、成し遂げたいクリエイティブなアイデアと制作テーマをまとめた撮影企画書での応募を募りました。選考は3か月かけて行われ、地域別に実施された一次、二次選考、さらに、外部審査員を招き実施された最終選考を経て、2025年1月に受賞15テーマを決定しました。
制作活動のサポートとして、「Global Grant Award(大賞)」受賞者の5名には10,000ドル相当の助成金を、「Regional Grant Award(優秀賞)」受賞者の10名には5,000ドル相当の助成金をご提供。さらに、制作に使用する機材として、富士フイルム ラージフォーマット デジタルカメラシステム GFX *1 を無償貸与させていただきました。そして、制作期間6か月を経て、2025年6月ついに15作品が完成しました。
本展では、「GFX Challenge Grant Program 2024」を通じて制作された受賞者15名の作品を一堂に展示いたします。世界各国から集まったオリジナリティあふれる写真・映像作品をお楽しみください。
*1 富士フイルム ラージフォーマット デジタルカメラシステム GFXとは35mm判の約1.7倍となるラージフォーマットセンサーを搭載し、豊かな階調表現と浅い被写界深度による立体的な描写を可能とした、異次元の高画質をさらに身近にする画期的なミラーレスデジタルカメラシステムです。
※ 助成金プログラムや受賞者および取り組んだ作品の詳細はこちらをご覧ください。
<写真展関連プログラム>
15作品の写真家によるメイキング映像
本メイキング映像を、ご来館の前にあるいはご覧になった後改めてご覧いただき、展示作品から何かを感じていただく参考にしていただいたり、ご来館が難しい方にも本展をお楽しみいただく機会にしていただければ幸いです。
- 15作品の写真家によるメイキング映像 (フジフイルム スクエア)
作品点数 : 全倍・全紙・半切サイズなど、カラー(またはモノクロ)、約100点以上の展示を予定しています。
・デジタルによる作品。
・展示作品は、描写性の高い富士フイルム製品「銀写真プリント」を使用。
・動画作品はモニターで上映します。
主催 : 富士フイルム株式会社
【巡回展】
| 富士フイルムフォトサロン 東京 | 2025年10月31日(金)~11月20日(木) |
■ 出展クリエイターと作品紹介
1. Global Grant Award 受賞者(5名)
セサル・グアルディア・アレマーニ César Guardia Alemañi (アルゼンチン)
「Echoes of Resilience(復興の響き)」
![[Image]「Echoes of Resilience(復興の響き)」](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_pic01.jpg)
Echoes of Resilience
©César Guardia Alemañi
(GFX Challenge Grant Program 2024)
「Echoes of Resilience(復興の響き)」は、1944年にアルゼンチンのサン・フアンを襲った壊滅的な地震と、それを機に表出した不屈の人間の本質に焦点を当てたプロジェクトです。困難な時代における人間の深い強さを捉え、最も暗い瞬間でも、相互の連帯とケアを通じて光を見出せることを思い起こさせます。
![[Image]セサル・グアルディア・アレマーニ](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_profile01.jpg)
セサル・グアルディア・アレマーニは、アルゼンチンのブエノスアイレス出身の写真家兼シネマトグラファー。彼の演出写真作品は、人間の本質とその最も内面的なプロセス、および人間関係に焦点を当てている。
クラウディア・グアダラマ Claudia Guadarrama (メキシコ)
「Rewriting memory. Intimate territories in resistance(書き換えられる記憶)」
![[Image]「Rewriting memory. Intimate territories in resistance(書き換えられる記憶)」](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_pic02.jpg)
Rewriting memory. Intimate territories in resistance
©Claudia Guadarrama
(GFX Challenge Grant Program 2024)
メキシコ・ユカタン半島の近代化と開発により、マヤの女性たちがその居住地と生活において直面している森林破壊と土地奪取は、止まることのない勢いで進行しています。このプロジェクトでは、彼女たちのレジリエンスと活動家としての取り組みを検証し、周囲に生きる生物の保護と多様性の維持に対して担う重要な役割を考察します。
ジャンルカ・ランチャイ Gianluca Lanciai (イタリア)
「Timeland(タイムランド)」
![[Image]「Timeland(タイムランド)」](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_pic03.jpg)
Timeland
©Gianluca Lanciai
(GFX Challenge Grant Program 2024)
「Timeland(タイムランド)」はサルデーニャ島の中心部への旅であり、この島が誇る驚異的な長寿の秘密を探ります。このプロジェクトでは、自然と古代からの伝統が結びつき、それらがまるで長寿の秘薬を宿しているかのような、独自のつながりを明らかにします。
鈴木萌 (日本)
「Kusari」
![[Image]「Kusari」](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_pic04.jpg)
Kusari
©鈴木萌
(GFX Challenge Grant Program 2024)
「Kusari」は岡山県で起きた、化学物質PFASによる水道汚染の物語です。汚染源となったのは水源のダム近くに放置されていた粒状活性炭の廃棄物で、そこから鎖のようにつながった化学物質が水源へと浸透し、いつの間にか人々の日常に影を落としていきました。このプロジェクトは、現地リサーチと、この水を日常生活で利用してきた人々から集められた証言を折り重ねながら語られる物語です。
レイニス・ホフマニス Reinis Hofmanis (ラトビア)
「Shared Horizon(分かち合う地平線)」
![[Image]「Shared Horizon(分かち合う地平線)」](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_pic05.jpg)
Shared Horizon
©Reinis Hofmanis
(GFX Challenge Grant Program 2024)
バルト海とロシアの境界地域における物理的・心理的な境界を調査し、その境界がバルト諸国のアイデンティティ、帰属意識、日常生活に与える影響を分析しています。
![[Image]レイニス・ホフマニス](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_profile05.jpg)
レイニス・ホフマニス(1985年生まれ)は、ラトビアのアーティスト兼写真家。彼の作品は、社会的集団、その行動、および周囲の環境への影響をテーマに探求している。
2. Regional Grant Award 受賞者(10名)
ダスル・リー Da-seul Lee (韓国)
「Under the Purple sky(紫の空の下で)」
![[Image]「Under the Purple sky(紫の空の下で)」](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_pic06.jpg)
Under the Purple sky
©Da-seul Lee
(GFX Challenge Grant Program 2024)
ビジュアルアーティストとして活躍する傍ら、農家も営むダスル・リーが、その一見両立しない立場を最大限に生かして、本来、畑から除去する必要のある雑草を育て、それを記録しました。
デイヴィッド・フルデ David Fulde (カナダ)
「Queer Lenses(クィアのレンズ)」
![[Image]「Queer Lenses(クィアのレンズ)」](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_pic07.jpg)
Queer Lenses
©David Fulde
(GFX Challenge Grant Program 2024)
かつて暗闇のバーに閉じ込められるように存在していたドラァグクイーンは、今や世界的な舞台に立っています。このプロジェクトでは、カナダのスラム街に響く独自の声を、レンズを通して捉えます。
ギャヴィン・マクスウェル Gavin Maxwell (英国)
「If The Land Could Speak (もし大地が語るなら)」
![[Image]「If The Land Could Speak (もし大地が語るなら)」](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_pic08.jpg)
If The Land Could Speak
©Gavin Maxwell
(GFX Challenge Grant Program 2024)
このプロジェクトは、世界中で増加している「自然の権利」に関する環境訴訟からインスパイアされ、劇的な気候変動の時代におけるヒンドゥークシュ・ヒマラヤ地域を調査し、自然界の精神を物語の主人公として描いています。
グレッチェン・ケイ・スチュアート Gretchen Kay Stuart (米国)
「The Oregon Otter Gap(オレゴンのラッコが語る現実)」
![[Image]「The Oregon Otter Gap(オレゴンのラッコが語る現実)」](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_pic09.jpg)
The Oregon Otter Gap
©Gretchen Kay Stuart
(GFX Challenge Grant Program 2024)
オレゴン州では19世紀の毛皮交易以来、ラッコが地域絶滅状態にあり、沿岸の生物多様性に脅威を与えています。このプロジェクトは、視覚的なストーリーテリングを活用し、世の中に溢れる誤解を紐解き、気候変動がもたらす課題が深刻化する前に警鐘を鳴らすこと。また、それらを解決する活動を加速させ、支援することが目的です。
ジャレッド・ワキニー Jared Wahkinney (米国)
「Peyote People(ペヨーテ・ピープル)」 【動画】
![[Image]「Peyote People(ペヨーテ・ピープル)」](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_pic10.jpg)
Peyote People
©Jared Wahkinney
(GFX Challenge Grant Program 2024)
「Peyote People(ペヨーテ・ピープル)」は、コマンチ族とペヨーテ(サボテン科の植物)の関係を題材にしたドキュメンタリーです。この映画は、テキサス南部でのペヨーテの収穫からオクラホマでの儀式での活用までの旅路を記録しつつ、これらの伝統を次世代に伝える重要性を強調しています。
カーリ・ブラウン Kahli Brown (ナイジェリア)
「Plastic Possibilities(プラスチックの可能性)」
![[Image]「Plastic Possibilities(プラスチックの可能性)」](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_pic11.jpg)
Plastic Possibilities
©Kahli Brown
(GFX Challenge Grant Program 2024)
ナイジェリアにおけるプラスチック廃棄物の、持続可能な解決策を記録するビジュアル・ストーリーテリング・プロジェクトです。このプロジェクトは、地域社会におけるプラスチック汚染に対処する地元の取り組み、イノベーション、住民による草の根運動を強調することを目的としています。
クリスティーナ・ニコロヴァ Kristina Nikolova (イタリア)
「Stabat Mater - The Ten Ages of Woman
(スターバト・マーテル — 女性たちの生涯 十の世代)」
![[Image]「Stabat Mater - The Ten Ages of Woman(スターバト・マーテル — 女性たちの生涯 十の世代)」](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_pic12.jpg)
Stabat Mater - The Ten Ages of Woman
©Kristina Nikolova
(GFX Challenge Grant Program 2024)
幼少期から高齢期までの女性たちの生涯を十の世代に分け、女性性を探求する作品です。各ポートレートは、身体が変化していく中で、精神の本質は不変であるという繊細な相互作用を捉えています。未加工の肖像画を通じて、女性たちの強靭さ、脆弱さ、そしてその変容を探求しています。
ルオ・フェイ Luo Fei (中国)
「Weaving Connections : The Vitality of Tajik Embroidery
(紡がれる絆 — タジク刺繍の命脈)」
![[Image]「Weaving Connections : The Vitality of Tajik Embroidery(紡がれる絆 — タジク刺繍の命脈)」](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_pic13.jpg)
Weaving Connections : The Vitality of Tajik Embroidery
©Luo Fei
(GFX Challenge Grant Program 2024)
このプロジェクトは、写真を通して個人の物語を伝えることで、伝統的な風習に息づくタジク刺繍の模様や文様を直接的に紹介し、この民族の人生における刺繍の重要性を浮き彫りにします。
安西剛 (日本)
「Ultra Giant Micro Plastic」
![[Image]「Ultra Giant Micro Plastic」](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_pic14.jpg)
Ultra Giant Micro Plastic
©安西剛
(GFX Challenge Grant Program 2024)
プラスチック汚染は深刻な環境問題にもかかわらず、マイクロプラスチックは小さすぎて、私たち自身の目で見ることはほとんどありません。本プロジェクトでは、マイクロプラスチックをクローズアップで撮影した巨大な写真と類型学的なアーカイブを制作することで、プラスチック汚染への新たな視点でとらえます。
![[Image]安西剛](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_profile14.jpg)
現代美術作家。千葉在住。キネティック・スカルプチャーや海洋プラスチックを通じて、人とモノの関係性を探求している。作品は、生命と無生物の境界を問いかけ、ブダペスト、金沢、ヒューストン、ベルリンなどで国際的に展示されている。
イー・シエン・リー Yi Hsien Lee (台湾)
「Scar Tissue(傷痕の組織)」
![[Image]「Scar Tissue(傷痕の組織)」](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_pic15.jpg)
Scar Tissue
©Yi Hsien Lee
(GFX Challenge Grant Program 2024)
台湾は現在、建築の転換期に直面しています。多くの建物が寿命を迎え、解体される段階に差し掛かっています。解体される際、他の建物に残される痕跡は、都市の傷跡のようなものです。これは一つのプロセスであり、独自の物語を持っています。このプロジェクトでは、それらを撮影し、周囲との関わりを観察し、分類していきます。
![[Image]イー・シエン・リー](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_profile15.jpg)
ロンドンで2年間インテリアフォトグラファーとして働いた後、YHLAAを設立。建築とインテリアフォトグラフィーに特化し、台湾を拠点に、国際的なクライアントと密接に協力して活動している。
■ 外部審査員紹介
アマンダ・マドックス Amanda Maddox
キュレーター、コンサルタント
![[Image]アマンダ・マドックス Amanda Maddox](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_judge01.jpg)
キュレーターで、以前は世界報道写真財団(ワールド・プレス・フォト)のリード・キュレーターやDCのコーコラン美術館やロサンゼルスのJ・ポール・ゲティ美術館で写真部門のアソシエイト・キュレーターを務めていた。 ドーラ・マール展(2020年)、ゴードン・パークス「The Flávio Story」展(2019年)「Now Then:Chris Killip and the Making of In Flagrante」展(2017年)、石内都「Postwar Shadows」展(2015年)など数多くの写真展を企画・共催。
レスリー・A・マーティン Lesley A. Martin
エグゼクティブディレクター(Printed Matter, Inc.)
![[Image]レスリー・A・マーティン Lesley A. Martin](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_judge02.jpg)
Printed Matter, Inc.のエグゼクティブディレクターで、『The PhotoBook Review』の創刊者。『Aperture』、『IMA magazine』、『FOAM』などで執筆。リチャード・ミズラックの『On the Beach』、川内倫子の『Illuminance』、アントワン・サージェントの『The New Black Vanguard』、サラ・クワイナーの『Glass life』など、150冊以上の写真集を編集。マーティンは2012年に「The Paris Photo – Aperture Foundation Photobook Award」を共同設立し、2020年には写真出版における顕著な功績に対して英国王立写真協会賞を受賞した。イェール大学大学院で教鞭をとる。
佐藤正子 Masako Sato
写真展企画制作、キュレーター 株式会社コンタクト
![[Image]佐藤正子 Masako Sato](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_judge03.jpg)
智大学文学部新聞学科卒業。PPS通信社入社後、写真展の企画制作に携わる。2013年、展覧会企画制作会社コンタクト設立。写真を中心とした展覧会の企画を中心に、ロベール・ドアノーの日本国内での著作権管理、編集企画にも従事。これまで、ロベール・ドアノー、ジャック=アンリ・ラルティーグ、牛腸茂雄、ソール・ライターなどの国内巡回展企画制作に従事。
ポリーヌ・ヴェルマール Pauline Vermare
写真キュレーター(ブルックリン美術館)
![[Image]ポリーヌ・ヴェルマール Pauline Vermare](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_judge04.jpg)
ニューヨークのブルックリン美術館の写真キュレーター。元マグナム・フォトNYの文化ディレクターで、ニューヨークにある国際写真センター(ICP)、ニューヨーク近代美術館(MoMA)、アンリ・カルティエ=ブレッソン財団のキュレーターでもあった。写真に関するインタビューやエッセイを多数執筆。ソール・ライター財団とキャサリン・リロイ財団の理事を務めている。
※ 写真展・イベントはやむを得ず、中止・変更させていただく場合がございます。予めご了承ください。
※ 祝花はお断りいたします。


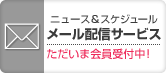

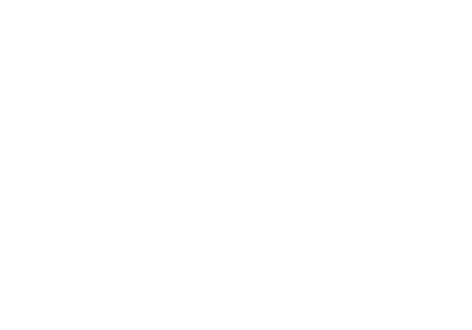
![[Image]クラウディア・グアダラマ](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_profile02.jpg)
![[Image]ジャンルカ・ランチャイ](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_profile03.jpg)
![[Image]鈴木萌](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_profile04.jpg)
![[Image]ダスル・リー](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_profile06.jpg)
![[Image]デイヴィッド・フルデ](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_profile07.jpg)
![[Image]ギャヴィン・マクスウェル](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_profile08.jpg)
![[Image]グレッチェン・ケイ・スチュアート](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_profile09.jpg)
![[Image]ジャレッド・ワキニー](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_profile10.jpg)
![[Image]カーリ・ブラウン](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_profile11.jpg)
![[Image]クリスティーナ・ニコロヴァ](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_profile12.jpg)
![[Image]ルオ・フェイ](/photosalon/pack/images/2512/o2512120123_profile13.jpg)